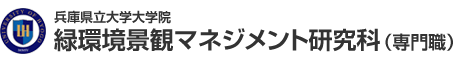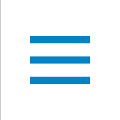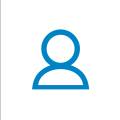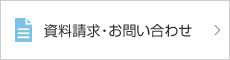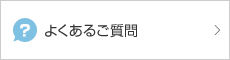1年前・後期【基礎】共通領域 フィールド植物観察演習Ⅰ・Ⅱ
この科目は、植物の適切な維持管理に必要な、植物の構造や機能の季節変化を、栽培目的に応じて理解することを目的にした必修科目です。植物分類・名称を理解し、植物を正確に同定する能力も身につけます。
授業では、開花期など生育ステージに合わせて、学内フィールドで実際の植物に触れながら使用方法なども説明します。


1年前期【基礎】共通領域 生活空間デザイン演習
この科目では、小さな鉢植えから個人庭園までの身近な生活空間を題材として、植物による空間デザインを行います。前半の授業では、苔や多肉植物を用いた寄せ植えづくり、小空間を彩るオーナメントづくり、コンテナ寄せ植えなどを行います。後半の授業では、「空間デザイン力」を修得するため、個人邸の庭園設計を行います。具体的には、空間情報の読み取り方、空間のデザイン、植物等の材料選定、図面の作成、プレゼンテーションなど、一連のデザイン作業を通じて、生活空間におけるデザイン技法を修得することを目的としています。




1年前期【基礎】活用デザイン基礎演習
この科目は、緑環境を中心とした景観デザインに関わる理論と、ランドスケープデザイン実務で必要となる製図等に関する基礎技術や表現力を修得するための演習です。具体的には計画・設計に関わる基本的な造形技術(作図、色彩構成、模型作成)の基礎トレーニング、また、景観デザインの実務で必ず必要となる製図技術ならびにコンピュータ・ソフトウエアの基礎トレーニング行います。この科目は、緑環境やデザインに関する学部以外の学部出身者を対象としたフォローアップの位置づけとなっています。
1年前期【基礎】景観計画デザイン論
この科目は、景観保全や景観資源の活用に視点を置いた景観デザインに必要とされる景観構築のあり方とその手法を学び、景観保全・活用・創出に関するデザイン的視点から見た分析力を身につけることが目的です。講義の中では、具体的な事例分析を通じて、緑環境による景観のつかみ方(分析)、生かし方(活用)、つくり方(創出)を論じます。
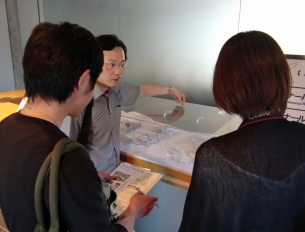

1年後期【応用】景観活用デザイン演習
この科目は活用デザイン領域の応用科目です。ランドスケープの展開手法と景観活用業務の実務を学び、デザインプランの作成を通じて「空間構成力」と「地域分析力」、「図面表現力」を養い、実務で必要となるランドスケープデザイン能力を修得することを目的としています。具体的には、実際にある場所を対象地とし、その場所の自然・社会・文化などの諸要素を分析した上で、資源を生かしたデザインコンセプトの形成、空間配置計画、詳細設計などの一連のデザインプロセスの経験を通じて、実務的なデザイン力と調整力を養います。



▶2015年度の授業成果(淡路市摩耶地区)
▶2016年度以降の授業成果(ランドスケープデザイン研究室HPにて紹介)
1年後期【応用】園芸植物活用演習
この科目は、人の健康や福祉のために造園・園芸植物を活用できること、伝統的日本庭園の魅力を伝えることができるようになること目的としています。授業では、淡路島内の農家での農業実習、造園・園芸植物を用いたクラフト、京都の伝統的日本庭園の見学などを行っています。



1年通年【応用】造園施工演習
この科目は、造園土木構造物の施工演習を通して、空間デザイン力、土木工、コンクリート工などに関する知識・技術を修得し、造園構造物の設計積算図書の作成ができるようになることを目的としています。具体的には、学内の実習フィールドにて、コンクリート工を含む造園土木構造物の施工演習を行っています。