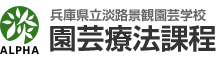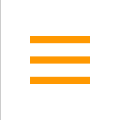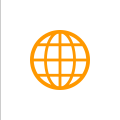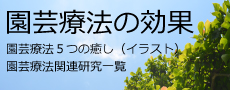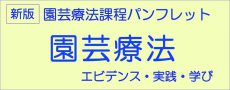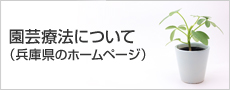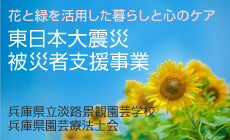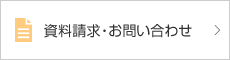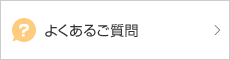園芸療法課程開講十周年となる本校のあゆみを、新聞記事で綴りました。
平成14年に開講してから、毎年15人以上の兵庫県園芸療法士を輩出してきました。
修了生は、日本の各地で、福祉・医療・教育などの分野で活躍しています。
今月よりシリーズで過去10年間の新聞記事のPDFを順次掲載して行きたいと思います。
ちょっと見えにくい記事もありますが、懐かしい新聞記事などがあるかと思います。
楽しんでください。
開講4年のあゆみ(平成14年~平成17年)
開講して4年間は、全国初の公立の園芸療法士を養成する学校としてスタートし、学生への教育だけでなく社会への啓蒙活動を中心に、兵庫県とともに歩んでいきました。
修了生の兵庫県園芸療法士の数が増えるとともに、各方面で活躍がはじまり、県内での知名度は徐々に高くなっていきました。
平成14年度の新聞記事
産経新聞 H14年10月9日「心を癒す土いじり お年寄りたちと交流」
平成14年は園芸療法課程開講した年です。開講当時から5年間は9月開講、8月修了でした。
公立機関で全国初の「園芸療法」の専門家育成課程が開講したことが、各社の紙面を飾りました。
第1期生入学は17名。倍率は4.1倍。
阪神淡路大震災の被災者の心のケアにも役立てようと導入された。
平成15年度の新聞記事
神戸新聞 H15年8月9日「園芸療法士16人巣立つ」読売新聞「園芸療法士1期生に16人」
神戸新聞 H15年9月3日「植物世話し心身回復支援」全国の15人入校式
第1期の修了生が16名巣立ち、全国で活躍を始めました。
緑を活用した園芸療法の力を解明するため、脳イメージングの先端技術であるMRIを使い科学的な研究も始まりました。
平成16年度の新聞記事
産経新聞 H16年6月6日「自然の癒し 今後を探る」 神戸新聞「淡路で国際サミット」
読売新聞 H16年10月13日「45歳の新入生奮闘 行政職推薦第1号」
読売新聞 H17年3月2日「園芸療法 庭先で育つ高齢者の元気 三重県が導入」
平成16年6月に、淡路島の東浦で植物とのふれあいを高めあう「園芸療法国際サミット」が開催され7カ国530人が参加しました。ニコル氏の講演もあり、盛況でした。
各県の養護学校や高齢者福祉施設・病院などで園芸療法の効果が認められはじめました。
平成17年度の新聞記事
神戸新聞 H17年5月8日「園芸療法士 植物で心身のリハビリ」
朝日新聞 H17年6月5日「心身の回復に園芸 認知症の改善に効果」
環境緑化新聞 H18年3月15日「兵庫県立淡路景観園芸学校 全寮制で実践を学ぶ」
平成17年は16人の園芸療法士が誕生し、物質より心の豊かさを求められる社会のニーズにこたえるように、福祉施設や病院に16人中13人が就職しました。
開講5年から8年までの4年間のあゆみ(平成18年~平成21年)
平成18年度に、修了生による「兵庫県園芸療法士会」が発足し、兵庫県園芸療法士のとしての自覚と日々の研鑽に励むための組織づくりができました。
それとともに兵庫県としても園芸療法を県内に広く活用していただくための普及促進事業がスタートし、その事業により県内の老人施設などで園芸療法士の雇用の拡大が大幅に増えました。
さらに、園芸療法の効果を脳神経学的に研究し、認知症高齢者の認知症進行予防に園芸作業が効果的である可能性を実証しました。
平成18年度の新聞記事
神戸新聞 H18年6月17日「園芸の楽しみを伝える人材を -来月ボランティア養成講座」
読売新聞 H18年10月8日「兵庫県園芸療法士会 淡路で設立総会」
神戸新聞 H18年10月27日「「園芸療法」の普及へ修了者派遣 今秋から試験導入 ~淡路島から順次拡大 本年度10箇所目標~」
朝日新聞 H18 年11月15日「園芸療法でお年寄りが生き生き! 導入促進へ 療法士を派遣」
神戸新聞 H18年12月26日「緑のリハビリ好評「笑顔戻った」効果実感 普及のカギは医師との連携」
この年に、修了生が増え、兵庫県園芸療法士会が発足し、現在も園芸療法士同志の情報交換や資質向上のための研修会などを開催している。
また、兵庫県も園芸療法を普及させる目的で園芸療法導入促進事業をはじめ、多くの施設で園芸療法の効果を分かっていただけるよう、園芸療法士によるセッション費用の半額負担する助成金事業を展開し始めた。
これにより、兵庫県内の施設で園芸療法の普及が促進された。
平成19年度の新聞記事
神戸新聞 H19年6月15日「園芸療法課程 内容などを紹介」
神戸新聞 H19年11月19日「寄せ植えで笑顔に 宝塚の特養 園芸療法士が訪問」
神戸新聞 H20年3月20日「園芸療法士の本格派遣丸1年へ 広がる緑のリハビリ 回数増加、科学的実証も」
園芸療法の普及・定着の歩みが確実なものになり始めました。
それととともに園芸療法のエビデンス研究の重要性が増し始め、より効果的な園芸療法への模索が始まりました。
平成20年度の新聞記事
朝日新聞 H20年4月23日「癒しの花作り学ぶ 園芸療法講座に51人」
神戸新聞 H20年6月27日「園芸療法で脳が活性化 認知症予防に期待」あす学会で発表
読売新聞 H20年7月3日「園芸作業で脳活性化実証」景観園芸学校専門員ら研究 認知機能低下予防に効果 学会で発表
朝日ファミリー新聞 H20年7月4日「脳の活性化にガーデニングが有効」兵庫県立淡路景観園芸学校の豊田正博講師ら研究グループが発表
園芸療法の普及とともに、園芸療法のエビデンス研究も始まりました。
脳神経学的な方面からの研究や、臨床における園芸療法の効果検証を行う質問紙作成など、園芸療法の効果を学術的に検証し始めました。
平成21年度の新聞記事
朝日新聞 H21年5月13日「淡路景観園芸学校 植物を用いて人と自然が共生するまちづくり 健康増進など学ぶ」
神戸新聞 H21年7月10日「園芸で脳機能活性化」記憶を刺激?会話ふえる
毎日新聞 H21年7月11日「園芸 認知症の進行抑制」 土混ぜる作業 脳血流増加 リハビリに安定的効果
園芸作業による認知症予防効果が徐々に認められはじめ、園芸療法のエビデンス研究が各方面で知られるようになりはじめた。
それとともに、マスコミでも効果について注目されるようになりはじめる。
開講22年から現在までの3年間のあゆみ(平成22年~平成24年)
園芸療法課程も開講8年を経て、100人を超す園芸療法士を輩出しました。
さらに平成24年度から、臨床現場で活躍されている方々が学べるコースとして通学制ができ(定員20名)、働きながら学べようになり、受講者も増えました。
また、兵庫県障害者支援課とともに農業分野での「障害者の就労支援のモデル事業」を展開するなど、新たな取り組みを始めました。この事業は現在も継続中で、園芸療法のノウハウを活かしたジョブコーチングの技術を農家やボランティアに教えるサポーター指導を担当し、淡路で「就労サポーター」の養成講座を行うなど就労支援事業を展開しています。
兵庫県園芸療法士も日本全国で園芸療法活動を展開し活躍しはじめたため、兵庫県だけでなく他県の新聞に取り上げられるなど、活動の場が広がりつつありました。
そのような中、東北で大震災が起こり、阪神淡路大震災後全国の皆様への返礼の精神で創設された本学の理念に則り、園芸療法による震災支援が被災地で展開されました。
園芸療法のノウハウを震災支援のストレスマネジメントに活かしていただくために実施した主な活動は、兵庫県に避難されている方々を対象に、被災地では支援活動に参加されている保健師・教員・指導員の・警察の方々を対象に、また仮設住宅にお住まいの方々対象に、園芸療法セッションや研修会活動を展開しました。そして、現在もその活動は継続中です。
平成22年度の新聞記事
神戸新聞 H22年4月5日「園芸療法サポーター養成講座の受講生募集」
神戸新聞 H22年8月28日「認知症高齢者らの園芸療法 野菜の話題で脳活性化 寝たきりの人に活用も」
神戸新聞 H22年10月11日「励み与え回復手助け インタビュー 草花がもたらす治療の効果は? 患者の歩み配慮しケア」
平成23年度の新聞記事
新婦人新聞 H23年4月7日「花と緑のあるくらしが、認知症のケアと予防にいい!」
神戸新聞 H23年4月19日「花、緑で被災者に元気を」県園芸療法士 県内避難者向け支援活動 ボランティア研修会
神戸新聞 H23年6月28日「障害者の就労を支援 県がモデル事業開始へ」
京都新聞 H23年9月4日「花と緑で心身のケアを 高齢者や障害者へ園芸療法士」全寮制で1年
上毛新聞(群馬)H23年9月4日「花と緑で心身機能を回復 園芸療法士を養成」兵庫の県立校
神戸新聞 H23年9月7日「岩手で園芸療法体験」 淡路景観園芸学校が実施
岩手日報新聞 H23年11月3日「ハーブ手浴で手軽な癒やし」 被災者支援に園芸療法を指導 心と体に植物の力
神戸新聞 H23年12月13日「障害者の就労仲介」 雇用拡大、来春から兵庫県開始
平成24年度の新聞記事
岩手日報新聞 H24年2月27日「花や緑の楽しみストレス緩和」盛岡で園芸療法研修会 講義やポプリ作り
日経新聞 H24年3月2日「園芸療法士、心癒す」阪神大震災後、兵庫県が養成 花の香り、笑顔に
日経新聞 H24年3月5 日「いまドキ関西 園芸療法士とガーデナー養成」
神戸新聞 H24年3月10日「花と緑で被災者ケア」 淡路景観園芸学校の教員、学生ら 2月岩手の仮設訪ね交流
朝日新聞 H24年5月18日「花いじり心いやして」 一緒に笑顔を咲かせたい
園芸療法課程10年のまとめ
園芸療法課程の10年間の歩みを新聞記事で追いかけてみました。
たくさんの新聞記事があり、すべてを掲載できなかったことをお詫びするとともに、多くの皆様のご支援と努力により、園芸療法課程が発展していったことを改めて実感することができました。
10周年を振り返り、更なるステップへ進みたいと思います。