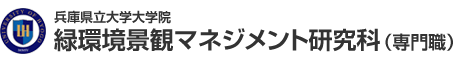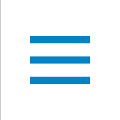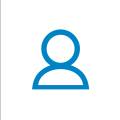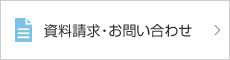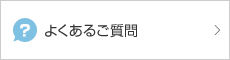景観園芸専門課程8期生 吉水 祥平さん
勤務先:大島造園土木株式会社
2006年より1年前期の授業「造園施工演習」の非常勤講師を担当
Q1:いまの仕事の概要を教えてください。
私の所属する会社は、愛知県を拠点にしている造園施工会社です。20代の頃は、民間企業の緑地において、植栽工事や維持管理工事を多数経験しました。30代になってからは、主要なお客様である自動車メーカーに3年間出向し、発注者の立場から造園施工について関わる機会を得ました。その後、名古屋市の公園工事の現場代理人を経験し、現在は20名ほどの技術者が所属する部署のマネージャーをやっています。マネージャーとしての主な業務は、官民の営業や見積対応、受注した業務に対してのメンバー配置や体制の構築、全社的な社員育成業務などです。
造園の技術者として得意な分野は、入社以来培った造園施工や樹木医としての経験が私のベースとなっていることから、植栽工事、緑地管理、樹木診断や植栽基盤診断、樹勢回復などです。
Q2:いまの仕事の面白いところを教えてください。
◆造園施工の面白さ
やはりモノづくりの面白さです。出来上がったときの達成感はもちろんありますが、土木や建築の現場とは異なり、造園の現場では出来上がったときが100%ではなく、メンテナンスで良くも悪くもなる点が、生き物を扱う唯一の建設業である造園の面白さだと思います。
これまでたくさんの現場を担当してきましたが、一つとして完璧な仕事はなくて、どの仕事でも「こうすればもっとよかった」「次はこうしよう」といった気づきがあって、それが次の仕事へ繋がっている感じです。
あとは、図面では表現しきれていない部分を現場の状況に応じて最適な手段が選択できる権限が施工の段階にはあるので、そのなかでどのように工夫してやっていくかを考えるのが面白い部分かと思います。
◆マネジメント業務の面白さ
一人でできる事は限られていますが、適切に配置したメンバーの働きによって、より大きな現場、より多くの現場を同時並行で進めていくことができる点が組織で働く醍醐味であり、マネジメント業務ならではの面白さかと思います。
Q3:進学しようと思ったきっかけは?
この業界に進むきっかけとなったのは、父親が植木の生産農家をやっていたことです。大学に進学した時点では家業にまったく興味はなかったのですが、就職活動をしていくなかで、父親と同じ分野で仕事をしてみたいと思うに至り、緑のことを学びたいと思うようになりました。そんななかで、淡路景観園芸学校を知り、進学するに至りました。
Q4:学校ではどのようなことを学びましたか?
計画から設計、施工、維持管理、その他の周辺分野まで、あらゆる授業や演習を一通り履修し、知見を広げました。そのなかでも、施工の分野に最も興味が出てきたので、施工演習だけでなく、当時のインストラクターの先生が企画されていた課外授業の施工演習で資材置場を整備するなど、大変貴重な経験ができました。
Q5:学校の魅力はどんなところにありますか?
緑に関するあらゆるものが、一通りそろっている点が大きな魅力だと思います。植栽されている植物、演習の道具や機械、図書室の書籍の数々、すべて使いこなせないほど充実していると思います。また、全寮制なので、やりたいことに集中できる環境も他の学校にはない魅力です。
Q6:学校で学んだこと、経験したことのどんなことが今役立っていますか?
淡路景観園芸学校では、緑に関する基礎的なことを学んでいたので、仕事にはスムーズに入っていけました。在学当時は、授業、演習だけでなく、モデルガーデンの出展やコンペなど、とにかくグループワークをする機会が非常に多かったため、仲間との関わり合いのなかでプロジェクトを進行するという経験が、社会人になる前の大きな予行練習になったと感じています。
Q7:卒業後、先輩や後輩とのつながりはありますか?
東海地方での仕事が多いので、学校関係者と一緒に仕事をする機会はほとんどありませんが、同窓会などの集まりに顔を出すと、各所で活躍されている先輩や後輩からいろんな刺激をいただけることが大変ありがたいです。最近では、タブレットを使用した3D測量について教えてくれた後輩と意気投合したことから、会社に来てもらったり、機器の導入にトライしたりと、同窓会を通じて自分の仕事の可能性を広げてくれたこともありました。
また、現役の学生とは、造園施工演習の授業で学校を訪問するたびに、施工の業界に興味を持ってくれる方に対して、私にできる限りの情報提供をしています。そして、私の所属する会社へ入社してくれる後輩も徐々に増えてきており、学校を通じての繋がりを感じています。
Q8:受験生へ一言お願いします。
この業界に入って15年以上経ちますが、日本でこの学校以上に緑について学べる環境はないと断言できますので、是非、その魅力を存分に味わっていただき、いつかどこかでご一緒できればこんなにうれしいことはありません。
(2024.09.10)