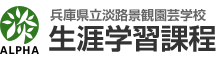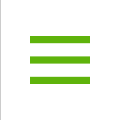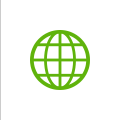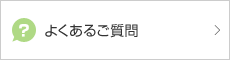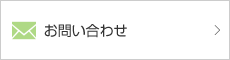今月は、バリアフリーのまちづくりと公園の利活用プログラムづくりをテーマに、インタープリターについても学び、公園の楽しみ方などを実習しました。
初日の5月16日は、花と緑の栽培実習として、メタセコ緑地の維持管理として1年草から宿根草への植え替えを行い、先に本科コースで播種していただいた一年草のプラグ苗の鉢上げを行いました。


田淵先生の説明 1年草を除き、土壌改良と整地を行う


田淵先生の指導のもとそれぞれに宿根草を植える
先月に播種をして育った苗の鉢上げを行いました。


2日目は午前中美濃先生からバリアフリーのまちづくりについて講義を受け、実際に車いすに乗ってフィールド内をめぐる体験実習も行われました。午後からは、緑地や庭園から観察フィールドを探す練習として、学内をまわりながら林先生からインタープリターとしての目の付け所などを伺いました。

 五感を使って森を観察します 紙コップで水中の生き物をすくい観察します
五感を使って森を観察します 紙コップで水中の生き物をすくい観察します
 演習室に戻って各班ごとに各々自分のプログラムの
演習室に戻って各班ごとに各々自分のプログラムの
作成に当たりました。
最終日の3日目は、昨日計画したプログラムについて、2グループに分かれ、各人7分ずつの持ち時間でインタープリターの実践を行いました。7分という短い時間では各人が調べたことの報告、発表のような形に終わってしまう人が多かったようですが、中には笹船づくりや森の中での体操を取りいれたり工夫されていました。五感を使って自然や何かに触れて観てもらうのはなかなか難しいようです。




最後に視聴覚室に戻って、実践の振り返りと意見交換及び先生からの講評などを聞き、今月の講座を終了しました。