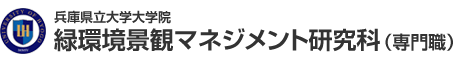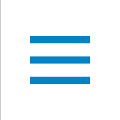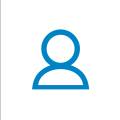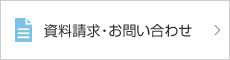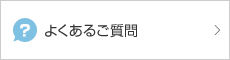こどもの日 小さな公園で見られる緑と子どものつながり
5月5日は「こどもの日」です。家族や地域にとって子どもたちの健やかな成長と幸福を願う特別な日です。しかし今、子どもたちを取り巻く環境に大きな変化が見られます。
減少する15歳未満人口と地域社会
総務省統計局は、2025年4月1日現在の15歳未満の人口は約1,366万人であり、前年より比べて35万人減少し、1982年から44年連続の減少となったようです(2025年5月4日公表)。このように、かつては地域にあふれていた子どもの声や鯉のぼりも見られなくなりました。一方で、子育て支援や子どもの居場所づくりは、地域において重要な課題として広がりを見せています。(総務省ホームページ:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei03_01000131.html)
こどもの居場所としての小さな公園の役割
1960年代の高度経済成長期において、日本の都市公園制度では、モータリゼーションが進展する中で、こどもが安全かつ身近に遊べる「児童公園(標準面積0.25ha)」の整備が急務となりました。「児童公園」は、住宅地のなかに最も近い距離で配置された小さな公園であり、公園の3種の神器と呼ばれた、滑り台やブランコ、砂場などの遊具が備えられていました。また当時、「交通公園」という国の施策で行った公園も全国各地で整備されました。「交通公園」は、子どもたちが安全に交通ルールを学べるよう計画された公園であり、公園の中に道路や信号機、自転車コースなどを備えた公園でした。
写真は、群馬県前橋市の「前橋こども公園(面積約4.8ha)」であり、1969年に「交通公園」として整備されましたが、施設の老朽化を踏まえ、2012年に再整備されました。これにより、現在でもこどもの安全な自転車の乗り方教室も行われるなど、身近なこどもの遊び場、緑の拠点としての小さな公園として維持されています。


今年の5月5日、再整備された「前橋こども公園」の姿は、多くこどもや家族づれで賑わっていました(下写真)。再整備された「前橋こども公園」では、芝生広場でピクニックを楽しむ家族、木陰で絵本を読む親子、複合遊具で遊ぶこどもなど、にぎやかな姿が見られ自由と創造性に溢れていました。


「こどもの日」に考える、未来のまちづくり
1997年の都市公園法施行令の改正により、「児童公園」は「街区公園」と名称を変更しました。少子高齢化が進む中で児童のみならず、高齢者をはじめ街区内の居住者の公園利用の実態を鑑みた結果です。
「こどもの日」は、未来を担うこどもたちを思うだけでなく、こどもたちを主役とする未来のまちづくりを、どのようにつくり、どのように継いでいくかを考える日でもないでしょうか?「こどもの日」に、木漏れ日のもとで小さな公園で、緑とつながるこどもたちの姿は、地域における未来のまちづくりの希望そのものではないでしょうか?