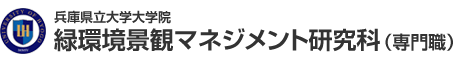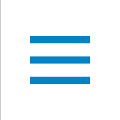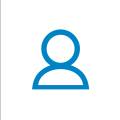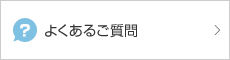日常化した大自然の風景
 アマゾンの奥深いジャングル、白い流氷が漂う北極海、地平線の彼方まで広がるアフリカの砂漠・・・こんな大自然の風景を実際に現地で見たことがある人は、それほど多くはないと思う。だが、こうした風景は、テレビや写真などのメディアを通じて人々の日常に入り込み広く知られている。それらは、人類が地球上に登場する遥か以前からそこに存在した、手付かずの神秘的な風景として人々に好まれるのだと思う。
アマゾンの奥深いジャングル、白い流氷が漂う北極海、地平線の彼方まで広がるアフリカの砂漠・・・こんな大自然の風景を実際に現地で見たことがある人は、それほど多くはないと思う。だが、こうした風景は、テレビや写真などのメディアを通じて人々の日常に入り込み広く知られている。それらは、人類が地球上に登場する遥か以前からそこに存在した、手付かずの神秘的な風景として人々に好まれるのだと思う。
もちろん、地球上の秘境に位置するこの種の風景の映像を一般の人々が広く見ることができるようになったのは、写真やカラー印刷やテレビが普及したごく最近のことなのだが、ここで問題にしたいのは、このような風景に対する価値観がいつごろどのようにして生じたのかということだ。手付かずの大自然は、人類が生活できない不毛の荒野に広がっており、それゆえ人為が及んでいないわけだが、そのことは、それらの風景が人類の生活には不都合な状態であることを意味し、少なくともユートピアの風景とはいいにくく、最悪の風景として捉えられたとしてもそれほど不思議ではないように思う。極地や砂漠や熱帯雨林などのいわゆる秘境の風景が好ましいものとして捉えられるようになった背景には、それなりの出来事があったはずだ。
別稿(やさしい風景学!4―「なぜ、日本アルプスと瀬戸内海はメジャーな風景なのか」ランドスケープデザイン60,108-111,マルモ出版)で、筆者はヨーロッパにおけるアルプスの風景の受容について概説したが、それが美しいものとして認識されるようになったのは18世紀前半のことであり、それまでアルプスはキリスト教教義の下で地球のイボやオデキのようなものだと考えられていたのである。アルプスの風景が美しいものとなった背景には宗教、科学、哲学の諸分野で革命的な出来事が蓄積されたことがあったわけだが、ここで問題にしようとする大自然の風景全般の発見は、やはりこの延長線上に位置している。それは、18世紀末から19世紀前半にかけてのロマン主義時代のヨーロッパでの出来事だったのである。
万葉の時代から日本人は、生活空間やその周辺に位置する身近な自然に深い関心を示してきたのだが、江戸時代以前の俳句や和歌、絵画を見れば明らかなように奥深い山岳、高原、湖、渓谷、蝦夷(北海道)などに広がる大自然の風景は完全に無視されていた。日本における大自然の風景の発見について語るためには、ヨーロッパから話を始めなければならないのである。
といっても、19世紀前半のヨーロッパにおいて、極地などの秘境への旅行は、まだ始まったばかりであり、写真技術も未発達だったので、秘境の大自然が直接的にその出来事の対象になったわけではない。ただし、秘境の大自然は、ロンドンやパリやベルリンで暮らす人々の目の前にもあったのである。それは、雲が漂う空だった。
18世紀までのヨーロッパの雲
 刻々と色彩と形を変えながら流れ去る雲は、たしかに人為の及びようがない神秘的な大自然のひとつであり、手付かずの秘境の大自然と途切れることなく繋がっている。
刻々と色彩と形を変えながら流れ去る雲は、たしかに人為の及びようがない神秘的な大自然のひとつであり、手付かずの秘境の大自然と途切れることなく繋がっている。
ヨーロッパにおける雲の発見については、佐原雅通が詳しく研究している。佐原によれば、ヨーロッパでは伝統的に天空は神聖な領域であり、キリスト教的には、「救済」「至福」「神の完全無欠」などのイメージと結びつき、そのことは、出エジプト記の「そのとき、雲が幕屋をおおい、主の栄光が満ちた」やヨハネの黙示録の「見よ、彼は雲に乗ってこられる」というようなキリストを語る表現からも読み取れるとされる。つまり、18世紀末までのヨーロッパの空は天使の住む世界だったのだ。
このような中で、眞岩啓子が指摘するように、絵画において、雲は宗教画、神話画、歴史画などの余白に軽微に描かれるにすぎず、イタリアやオランダでは17世紀になると風景画が台頭していたが、ここでも雲が綿密に観察されて描かれるようなことは稀であり、雲は人々にとって、少なくとも観賞の対象ではあり得なかったのである。
ところが、美術、文学、科学の分野でイギリスとドイツを中心として同時発生的に雲に対する熱狂的とも言える関心が突如高まったのである。そのムーブメントの中心は佐原によれば、1780年から1840年の間にあるとされているが、ここでは19世紀前半に焦点をあてて概観したい。
19世紀のヨーロッパの雲
 まず、イギリス人気象学者のルーク・ハワード(1772-1864)は、「雲の変容について、またその生成、浮遊、消滅の法則について」と題する論文を1803年に「哲学雑誌」に連載し、予想外の反響と評価を受ける。ここで雲は巻雲、積雲、層雲などに分類された上で、神と無関係に生成や消滅することが明らかにされたのである。
まず、イギリス人気象学者のルーク・ハワード(1772-1864)は、「雲の変容について、またその生成、浮遊、消滅の法則について」と題する論文を1803年に「哲学雑誌」に連載し、予想外の反響と評価を受ける。ここで雲は巻雲、積雲、層雲などに分類された上で、神と無関係に生成や消滅することが明らかにされたのである。
ゲーテ(1749-1832)はハワードの論文をドイツ語訳で読み、雲の研究に熱中するようになる。ゲーテのハワードに対する敬意は「ハワードによる雲形」や「ハワードへの敬慕」と題する詩となり、1817年には、雑誌「自然科学一般のために」において公表される。
こうして、ハワードの研究はゲーテを介してドイツ・ロマン派風景画家のフリードリヒ、カールス、ブレッヘン等に知られ、大きな影響をもたらすこととなる。
カスパル・ダーヴィト・フリードリヒ(1774-1840)は、1807年から1810年にかけて、「山上の十字架」や「海辺の修道僧」など、すでに画面の過半の面積に空と雲を描いたドラマティックな風景画を発表していたのだが、たとえば1820年の「漂う雲」では風に流されながら形を変える山上の雲自体をモチーフとしたように、雲への感心はますます高まっていく。
一方、イギリス・ロマン派風景画家の中で、雲を最も多く描いたのは、「私は雲の男です」と自称したジョン・コンスタブル(1776-1837)であった。佐原によると、コンスタブルは科学的な視点から雲の正確な描写を追求し、そのスケッチには日時、天候、風向、風力などのデータが記録されていただけでなく、雲の色を計測するための色とりどりのフラスコが用いられたという。こうして、コンスタブルは1820年代に膨大な量の雲の習作を描き、それらは科学的に見てもいたって正確なものだったのである。
そして、イギリスを代表する画家ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー(1775-1851)もまた、雲を主たるモチーフのひとつとした。フランス生まれのイタリアの画家クロード・ロラン(1600-1682)が、当時のイギリスで圧倒的な人気を得てピクチャレスクに大きな影響をもたらしたことについては、前述の別稿で説明したとおりなのだが、ターナーの1810年代の作品は、ロランの作品と見分けがつかないほど似たものであり、その強い影響下にあったことがわかる。しかし、ターナーの1820年代から40年代にかけての多くの作品は、画面の過半に光に満ち溢れた幻想的ではあるけれどダイナミックでリアルな雲が漂う空を描き、独自の世界観を構築する。また、ターナーの光の捉え方は、後に展開するフランス印象派に繋がるものでもあった。
ここで登場するのがイギリス人美術評論家のジョン・ラスキン(1819-1900)である。ラスキンは、ターナーを評価し美術史におけるその位置づけを確立したことでも知られているのだが、1843年に刊行した「近代画家論」の中で「雲の真実」と題する章を設けて、雲を文学として表現した。その一部を下記に示すが、ラスキンはこれにより、それまで絵画や文学の中で、型にはまった表現でしか描かれなかった雲が、実際にはきわめて多様で変化にとんだものであることを人々に気づかせたかったのである。
「雲の色彩は、千変万化において驚異的なので、それらには特に留意せねばならない。かなりの数の巻雲が空にある時に、次の日没を見守るならば、特に天頂の辺りに、あなたが見るものは、空では二インチ離れても同じ色彩のままではないということである。ある雲は冷たい青色の暗い側面があり、周縁は乳白色であるし、またさらに太陽の近くの別の雲は、オレンジ色の下側と金色の縁取りなっている。これらが空の青さと混じって、その青さに移り変わるのを、あなたは見ることだろう。その青い部分をあなたはより暗い雲の冷ややかな灰色と識別することができない処がある。そして、その青さにはグラデーションが広がって、それが今は純粋で深いかと思ったら、次の瞬間は淡くか弱くなる。」
この一文は、後述する20世紀初頭の日本の雲に大きな影響をもたらすこととなり、重要なのだ。
19世紀初頭の雲をめぐるヨーロッパの社会状況
 さて、ここまでに、1803年から1843年にかけての雲を巡るヨーロッパの出来事を概観してきたのだが、次に、なぜ彼らが雲にはまってしまったのかについて考えてみたい。
さて、ここまでに、1803年から1843年にかけての雲を巡るヨーロッパの出来事を概観してきたのだが、次に、なぜ彼らが雲にはまってしまったのかについて考えてみたい。
そのためには、当時の社会状況を少し把握しておく必要がある。1761年のルソーの「新エロイーズ」や1786年のゲーテの「イタリア紀行」において、アルプスの風景が賞賛されたことについて前述の別稿でふれたように、18世紀半ばに入るとそれまでキリスト教教義の下で魔界だと考えられ嫌われていた大自然は人々にとって関心の的になっていた。またこの時期、地質学が大きく前進し、岩石から推測した地球の歴史が、聖書に示されたものより大幅に古いことが判明していた。佐原によると、聖書の天地創造は、当時、「紀元前4004年10月22日の土曜日」とされていたのであり、地質学の発展は聖域であった聖書の歴史を塗り替え、キリスト教の価値体系を根底から覆す推進力になったとする。
つまり、16世紀のコペルニクスの地動説、17世紀のガリレオの天体観測など、それまでにもキリスト教の権威を揺るがす様々な大事件があり、それらはその都度なんとか封じ込まれてきたのだが、18世紀後半に入ると、教会は科学が次々にもたらす新たなものの見方をもはや簡単には処理できなくなっていたのである。
さらに、斎藤隆文は、イギリスの政治評論家ウィリアム・ゴドウィン(1756-1836)のように公然と神を否定する立場をとる人々が現れ、キリスト教が動揺したことを指摘する。
19世紀初頭のこのタイミングに、ハワードの雲の論文は発表された。人々はそれに飛びついたのである。このあたりのドイツにおける状況について、佐原は、1830年代から40年代の文化生活を際立たせる特徴として、「様々な自然科学に対して断続的に激変する精神的な関心」を指摘する。具体的には、「通俗科学読物」が氾濫し、自然科学の書籍が常にベストセラーになっていたのである。
画家や文学者は雲に何を見たのか
 以上が、当時の社会状況の概観だが、次に、画家や文学者たちが、雲を描くことにより一体何を表現しよとしたのか考えてみたい。もちろん彼らは雲だけを描いていたわけではない、基本的には山岳、海洋、荒野、田園などの大自然の風景を描いていたわけだが、ここでは、その中で必ず描かれることになる雲に着目して議論しているのである。
以上が、当時の社会状況の概観だが、次に、画家や文学者たちが、雲を描くことにより一体何を表現しよとしたのか考えてみたい。もちろん彼らは雲だけを描いていたわけではない、基本的には山岳、海洋、荒野、田園などの大自然の風景を描いていたわけだが、ここでは、その中で必ず描かれることになる雲に着目して議論しているのである。
まず、画家についてだが、佐原は、フリードリヒの鋭敏な感性は荘厳な自然景観の中で、大気、雲、植生、花崗岩に内在する「至高の創造主」すなわち神と交感していたとし、コンスタブルは自然の生成力が織りなす調和を眼前にして、「神-人間-自然」というキリスト教的構造を超越した奥深い自然法則の認識に到ったとする。また、千足伸行は、ターナーの芸術はある意味で「創世記」のドラマの再現だと解説している。
これら3人の雲を描いた代表的ロマン派風景画家は、共通して自然の中に天地創造の源と「神」を見たのだということができそうだ。そして、その「神」は、科学によって解説され得る性質をもつものだったのではないのだろうか。彼ら3人は、風景を描くことにより、そんな「神」をテーマとする新たな宗教画を描こうとしたのでは。
次に、文学者についてだが、ゲルノート・ベーメは、ゲーテは汎神論者であり、ゲーテにとって、雲は霊的なものが映し出されたものなのだとする。ゲーテもまた前述した画家たちと同じように雲の中に「神」を見たのである。
また、横川善正は、ラスキンの考え方は、自然を見えるとおりありのままに忠実に写実すべきだというものであり、その根拠として、金子孝吉は、ラスキンが自然の中に「神」を見出していたからにほかならないのだとする。
こうして、当時のロマン派の画家や文学者は、大自然を精密に描写することに価値を認識したのである。なぜなら、科学という新たな領域の発達により、大自然は「神」としての性質を付与されたからなのだ。このような中で、雲はもっとも身近な大自然として人々の心を捉えたのであった。
大自然という新たな「神」に照らされた雲
 そして、この部分における最大の問題は、彼らが大自然の中に見出した「神」と、キリスト教の神との関係性なのだと思う。雲について考えるなら、もともと雲はキリスト教上の神の領域に位置していたのに、「大自然の神」の登場と同時に、全く異なる捉えられ方をされたわけだから、やはり両者の神は明らかに異なるものなのではないのだろうか。
そして、この部分における最大の問題は、彼らが大自然の中に見出した「神」と、キリスト教の神との関係性なのだと思う。雲について考えるなら、もともと雲はキリスト教上の神の領域に位置していたのに、「大自然の神」の登場と同時に、全く異なる捉えられ方をされたわけだから、やはり両者の神は明らかに異なるものなのではないのだろうか。
このあたりについて、斎藤は、ロマン派の芸術家たちにとっては、大自然は「神」と呼んでも一向に差し支えないものであったのだが、キリスト教社会においては神といえばキリスト教の神以外にありえないために、そう呼べなかっただけなのだとする。
つまり、ロマン主義は、当時の著しい科学の発達を背景にして、大自然の中にキリスト教とは異なる新たな「神」を見出したのだが、キリスト教文明の厚い価値観の壁を打ち破るまでには至らなかったのである。
ただ、そのプロセスの中で、雲はひと時光り輝いたのだ。
19世紀までの日本の雲
ここまでに19世紀前半のヨーロッパにおける雲を巡る出来事を概観した。雲が注目されるようになる背景には、科学の台頭とそれにともなうキリスト教の動揺があった。そして、今日のヨーロッパ人が雲を見てその美しさに感動するとすれば、そのきっかけは、19世紀前半のロマン主義にあるのだということができるのだと思う。これは、雲についてだけでなく、冒頭で述べたように極地や砂漠や熱帯雨林などのいわゆる秘境の風景など大自然の風景全般に対して言えることでもある。
それでは、日本では、雲はどのようにとらえられてきたのだろうか。
清少納言(966-1025推定)は「枕草子」の中で、「春は曙。やうやうしろくなりゆく山際、少しあかりて紫立ちたる雲の細く棚引きたる」「雲は白き。むらさき。黒きもをかし。風吹くをりの雨雲」「月のいとあかきおもてにうすき雲、あはれなり」などとしている。また、平沼洋司は、8世紀に編纂された万葉集に収められた4,500首余りの長短歌のうち、970首余りに、雲、雨、露、霧、霞、霜などの気象現象が歌われているとする。
以上のように文学において雲は様々に描かれているのだが、19世紀以前の絵画や版画において雲は背景の文様にすぎずリアルに観察された形跡はほとんど見られない。内田英治は、雲を比較的リアルに描いた画家として、円山応挙(1733-1795)や、葛飾北斎(1760-1849)などをあげているが、孤立対流雲のきめ細かい表現が現れてきたのは江戸後期の19世紀後半からだとし、西欧からの影響を指摘する。ちなみに、北斎は、「富嶽三十六景」のうち一般に「赤富士」と呼ばれている「凱風快晴」に波状高積雲を精緻に描いたが、この作品は1831年から1835年頃に描かれている。これはロマン派が雲を描いていた時期と完全に一致し、北斎は同時期から遠近法やヨーロッパの顔料を使用していることなどをふまえると、ロマン派の影響が間接的に存在した可能性は否定できない。ターナーと北斎が同じ日に雲を観察していたと思うと愉快ではある。
このように、雲の描かれ方は文学に比べて美術は低調ではあるものの、これらのことから、日本ではヨーロッパと異なり古来より雲を様々に観賞し楽しんできたと考えるのは間違いではないと思う。平沼は、ヨーロッパにおいて雲の美しさが発見されたのは18世紀末から19世紀にかけてであるのに対し、日本では古事記や万葉集の時代から雲は美しいものであったとする。加えて、日本が歴史的にキリスト教の普及率が一貫してきわめて低い特殊な国であることをふまえれば、19世紀前半のヨーロッパにおける雲を巡る出来事と日本は無関係のように思えるのだが、実はそうではないのである。
20世紀初頭の日本の雲
それは、1898(明治31)年から1900(明治33)年頃にかけて、浅間山山麓で始まっていた。ラスキンが1843年に刊行した「近代画家論」の中で「雲の真実」と題する章を設けて、雲を表現したことについては、前記しその一部を引用したわけだが、この時期、日本でそれが読まれ始めていたのである。
徳冨蘆花(1868-1927)と島崎藤村(1872-1943)は、ほぼ同時期にお互いそのことを知らずに、ラスキンの「雲の真実」に触発されて雲に関する文章を書き始めた。金子はこのあたりの経緯について詳細に研究している。徳冨は伊香保で、島崎は小諸で雲に取り組んでいた。
徳冨の雲は、そのごく一部を引用すれば、「空は淺碧に晴れつ、其根方に紫色の の如き片々の雲ありて俘めり。小野子子持より赤城にかけて渦まける白雲-藍色の隅ある-銀帯の如く一長列をなして山腹を纏ひ、小野子子持の頭-青緑の膚に藍色の蔭ある-宛ながら俘島の如く空に現はる。暫く見て居る程に、赤城の麓なる雲は、徐々に東南に向ひて大軍の動くが如く動き始めたり。綿々蓬々として渦まき簇がりつつ、次第に利根の流れに沿ふて下り初めぬ。然も先陣已に動き初めたるに、小野子子持の下、吾妻川の谷に屯せる雲は。猶牢乎として動かず」というようなものであった。
島崎の雲は、これもそのごく一部を引用すれば、「飛騨の山々のかなたに傾ぶける夕日の上には薄紫の雲集まり、すこしく離れては白色、灰色の雲のかたち、さながら猪鼻のごとく眺めらるるもありき。おのづと夕日に近き青空は薄き黄金の色にかはり白かりし雲も灰色と紫色とを帯びて、夕映にうつりかがやく雲縁は紅隈のごとくに見えぬ」というような感じなのである。
それぞれを徳冨は1900(明治33)年8月に刊行した「自然と人生」の中で、島崎は同年同月に刊行された雑誌「天地人」に「雲」というタイトルで公表したのであった。
金子は徳冨について特に詳しく調べており、徳冨の雲にまつわる表現の背景について、大自然を通じて神を見、神を感じるためであったとし、「萬有は神の聖書だ。自分は自然を通じて神を見たい。」という徳冨の言葉を引用している。
徳冨のこの言説は、まさに、ヨーロッパのロマン主義者たちが考えていた、あるいは考えようとしていた言葉なのではないのだろうか。ただ、当時のキリスト教社会の中で、彼らにとってはストレートに言えない言葉であったのかもしれない。
日本における大自然の風景の発見
そして、明治時代末の、こうした文学のムーブメントは、美術とシンクロしつつ同時進行していたのである。
大下藤次郎、三宅克己、吉田博、武内鶴之助というような画家たちもまたラスキンに触発されていた。大下は1904年に、地平線を画面の低い位置に設定し、画面いっぱいに穏やかではあるがアクティブな雲を生き生きと描いた「秋の雲」を発表し、武内は1911年に、灰色の雲間からわずかに水色の青空が垣間見える画面全てが空からなる「雲」を発表している。それらは、まさにフリードリヒやコンスタブルの日本バージョンなのだ。
これらの画家の中で特に重要なのが大下(1870-1911)である。大下は1905(明治38)年に、水彩画の団体会派「春鳥会」を創設するとともに、美術雑誌「みずゑ」を創刊し、現在、雑誌「美術手帖BT」を刊行する美術出版社を創業するなど、美術界に重大な足跡を残しただけでなく、西田正憲によれば、森鴎外、志賀重昻、小島鳥水、田山花袋、柳田国男、国木田独歩などと広く交遊し、当時の文化に大きな影響力を発揮した。
このように単なる画家ではなかった大下なのだが、大下が描いた絵はもちろん雲だけではなかった。西田によると1906(明治39)年から1910(明治43)年にかけて、当時の日本の秘境といえる、磐梯山、上高地、尾瀬、甲州白峰(白根三山)、十和田湖などを周り、風景画を描いたのである。それらは、明治20年代まで日本にはなかったロマン主義的な精緻な風景画であり、自らの「みずゑ」に掲載し、広く知られるものとなる。
西田は、日本では、紀行文学リードする形で、新しい自然景の発見と普及定着が進んでいたのだが、大下が1908(明治41)年に臨時増刊号『みずゑ』44号において、自らの風景画を掲載した尾瀬の特集を組み、これが、尾瀬を広く知られるものとしたことを指摘した上で、大下の描く風景画が、奥地の「原生景」の普及に関し、広く影響したとする。
おそらく、『みずゑ』44号で示された大下が描いた尾瀬の風景は、今日テレビなどのメディアを通じて人々に広く親しまれている極地や砂漠や熱帯雨林など秘境に所在する大自然の風景の最初のひとつだったのだと思う。こうして、それまで、存在すらあまり知られず、長い日本の歴史の中で一貫して無視され続けてきた、「原生景」が、神秘的な風景として人々に受容されていくのである。
日本における大自然の風景に対する価値観の出所
ここまで雲を手がかりにしながら、大自然の風景の受容について、19世紀前半のヨーロッパと、20世紀初頭の日本における出来事を概観してきた。
日本人はヨーロッパ人と異なり古くから雲の美しさを楽しんでいたのは確かな事実なのである。しかし、ヨーロッパ人が19世紀初頭に発見した雲の美しさに20世紀初頭の日本人が鋭敏に反応した事実は、両者の雲に対する認識の質が異なるものであることを示している。
19世紀までの日本の雲と20世紀以降の日本の雲の美しさはおそらく異なっているのだと私は考えている。つまり、清少納言が見た雲は伝統的な日本あるいは東アジアの雲であり、徳冨蘆花や島崎藤村、大下藤次郎らが見た雲はそれとは全く異なるロマン主義の雲だったのである。
そして、今日、私たちが見ている雲もまたロマン主義の雲であり、そのロマン主義が、私たちにたとえば尾瀬のような大自然の風景を美しいものとして認識させる原動力になっている可能性が高い。
ロマン主義は難解な領域であり、その正体は謎に包まれているけれど、それは過去のものではなく、今なお世界規模でアクティブな状態にあるのではないかと思う。
今日、私たちが大自然の風景を美しいものとして受容する背景に、たとえば、その一要素としてハワードの雲の論文に熱狂したゲーテの影響があるということは可能なのである。そして、さらにその背景には、科学の進展にともない大自然がキリスト教に脅威をもたらしたという歴史的経緯がある。
おそらく、大自然の風景に対する価値観の源泉は、科学と宗教の関係性の中にあり、両者が対立や摩擦を起こした時、すなわちロマン主義時代に、それが現出したのだと思う。
日本は、歴史的に科学と宗教の対立や摩擦を経験したことがなく、ヨーロッパにおけるその結果を「近代化」の中で「輸入」したにすぎない。今日一般に普及している大自然の風景に対する価値観の多くの部分は、「ヨーロッパ産」のものであり、江戸時代以前の日本の伝統とは概ね断絶したものなのだと思う。
日本には、もともと日本独自の大自然に対する価値観が存在し、それが今なお息づいているという考えは幻想に近く、むしろロマン主義の大自然に対する価値観が今なお息づいていると考えた方がより的確なのだ。
もちろん、人間が遺伝子レベルで普遍的に大自然の風景全般を好むということはありえないのである。大自然の風景は、それを好ましいと感じさせるソフトウエアがなければ無視されるだけなのだ。ここで論じてきたのは、私たちが現在、大自然の風景を見るために使用しているソフトウエアの出所についてなのである。
●参考文献
内田英治(1993)日本絵画の雲描写の構図を考える,天気40(12),907-912
金子孝吉(2005)徳富盧花による伊香保の自然描写について -『自然と人生』「自然に對する五分時」を中心に,滋賀大学経済学部研究年報12,123-148
ケネス・クラーク,佐々木英也訳(1998)風景画論―改訂版,岩崎芸術社
ゲルノート・ベーメ・武田利勝訳(2005)雲と気象-ハワードとゲーテの雲の学説に見る「気象の現象学」の萌芽 ,モルフォロギア27,66-75
斉藤隆文(2004)人と自然のハーモニー-芭蕉とイギリス・ロマン派,大阪外国語大学英米研究28,7-24
佐原雅通(2000)シュティフターとカール・グスタフ・カールス-芸術と科学の統合,東海大学紀要・外国語教育センター 21,307-315
佐原雅通(2004)ロマン派風景画とエコロジー-シュティフターのエコロジー思想の起源,東海大学紀要・外国語教育センター 24,81-96
佐原雅通(2005)ドイツ・ロマン派風景画の植生の発見-C.D.フリードリヒ,A.v.フンボルト,C.G.カールスが自然に見た神性-東海大学紀要・.外国語教育センター25,51-69
ジョン・ラスキン,内藤史朗訳(2003)芸術の真実と教育[近代画家論・原理編I],法藏館
千足伸行(1993)イギリスのロマン主義絵画,世界美術大全集20,小学館,233-241
西田正憲(2003)明治後期の風景画家アルフレッド・パーソンズと大下藤次郎による自然景の発見,ランドスケープ研究66(5),393-396
平沼洋司,武田康男写真(2001)空を見る,筑摩書房
眞岩啓子(2000)ゲーテとハワードの雲,上智大学ドイツ文学論集37,3-21
横川善正(1983)ジョン・ラスキンと自然 -「ピクチュアレスクなるもの」を背景として,金沢美術工芸大学学報27,91-103
●写真キャプション
(1)フリードリヒ(1820年作)漂う雲,ハンブルク美術館
(2)コンスタブル(1828年作)ハムステッド・ヒースの丘の池,クリーブランド美術館
(3)ターナー(1831年頃作)難破船に向かう救命ボートとマンビー装置,ヴィクトリア・ア
ンド・アルバート美術館
(4)大下藤次郎(1907年作)穂高山の麓,東京国立近代美術館
(5)大下藤次郎(1904年作)秋の雲,島根県立石見美術館
(6)大下藤次郎(1907年作)六月の穂高岳,市立大町山岳博物館