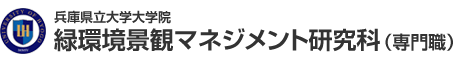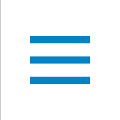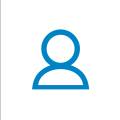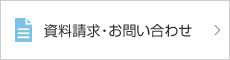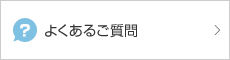本校での主な行事を執り行う「多目的ホール」という場所があり、その入口ロビーの坪庭に、2年程前から、”大きな黒いハチ”たちがいます。
 坪庭はガラス戸の外にあるので、このハチの存在に気づくことはほぼありませんが、坪庭に一歩出てみると、大きな羽音と、その数の多さ、そして、こちらに向かって来る(少し人間を気にしてる様子)ので、恐怖を感じるかもしれません。
坪庭はガラス戸の外にあるので、このハチの存在に気づくことはほぼありませんが、坪庭に一歩出てみると、大きな羽音と、その数の多さ、そして、こちらに向かって来る(少し人間を気にしてる様子)ので、恐怖を感じるかもしれません。
その坪庭は、三方を高い壁に囲まれ、手前はロビーの大ガラス、外部とはかなり隔絶されていると思われる環境にあります。
設計と施工は、沈先生の研究室のTさん中心で、淡路瓦をふんだんに使い、植物といえばジャノヒゲ程度、およそビオトープとは無縁と思われる環境で、Tさんはもちろん、指導教官の沈先生や、協力した教職員たちも、誰が生き物や淡路の自然環境のつながりを想像したでしょう!


この”大きな黒いハチ”たちは、地面に1cmほどもある大きな穴をあけ、その穴の奥で卵を生み、せっせとアルファガーデン(本校の庭園)に飛んで行って、その毒針でバッタ類などに麻酔を施し、大変な思いをしながらも、それらを穴の中に貯蔵しているようです。そう、「狩り蜂」と呼ばれるハチの仲間ですね。
その後、親バチたちは最後に穴に土で蓋をするのですが、力尽きて死んでしまいます。
やがて月日が経ち、何も知らずに生まれたハチの幼虫たちは、親バチたちが残してくれた新鮮なエサを食べ、育ち、サナギになります。やがてサナギの殻を破り、大きな穴を開けて地表に出てきます。このときまで、サナギの殻を引きづっているようで、穴から出た瞬間に脱げるんでしょうか、地表にはたくさんの抜け殻が散らばっています。
この特殊な環境は、Tさんが目指した淡路瓦中心の無機質な、生き物の生活環境とは無縁とも思える貧栄養の地面がむき出しであることを魅力と考えた親バチたちによって発見され、子育ての場になったのですね。
調べてみると、フクイアナバチまたはその近縁の比較的希少な種類のハチのようです。
淡路景観園芸学校/兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科のキャンパスは、こんな思いがけない生き物の営みを身近に感じられる希少なキャンパスでもあります。