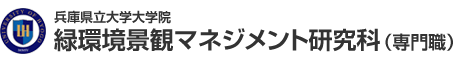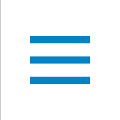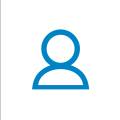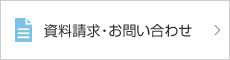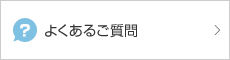以前の教員コラムで僕は “当研究科に入学したら,2年間の島暮らし・里山暮らしをもれなく体験できる” と書き,その体験の例として,学生寮での薪ストーブを使う暮らし(2022年1月)や,キャンパス周辺の里山で様々な絶滅危惧種に触れること(2024年4月)を紹介した.ちょっと意識すれば,里山のさまざまな魅力や現状に触れられるのが当研究科に入学する利点のひとつ.今回のコラムでは,島暮らし・里山暮らしで触れられる体験として,ドロナガシについて紹介したい.

ドロナガシとは,稲刈りが終わったあとの農閑期にため池の水をぜんぶ抜いて,池の底にたまった泥や砂を取り除く(流し出す)作業のことだ.池底には,上流から流入する砂泥のほか,枯れた植物が分解された腐植などが厚く堆積している.これを取り除くことによって,池の貯水量を確保し,水質を改善することができる.水を抜くので,外来生物の駆除などもついでにおこなえる.全国的には「カイボリ」と呼ばれることが多いようだが,淡路島では「ドロナガシ」「ゴミナガシ」で通じる.
かつてこの作業は,ため池の田主(たず)(その池の水をつかう農家の集まり)だけで行われる行事だったが,農村の高齢化や人口減少によって徐々に実施がむずかしくなってきた.最近では漁師も参加しておこなうようになっている.漁師の人たちは,ため池の泥(に含まれる栄養塩類)が海まで流れ下ることで海苔の色づきがよくなったり,魚が増えたりすることを期待して参加する.ドロナガシには人手が必要だ.それで当研究科の学生たちもドロナガシに参加するようになった.
ドロナガシは,事前に池の樋(ひ)を抜いて,数日をかけて徐々に水位を下げることからはじまる.十分に水位が下がったら,いよいよ本番である.
ドロナガシの本番は2日間かけておこなわれることが多く,1日目は「コイトリ」,つまり,浅くなった池に入って,コイ・フナ類・ウナギ・オオクチバス・ブルーギル・タイワンドジョウ・モクズガニ・イシガメ・クサガメなどのいきものをつかまえる.かつては,つかまえたフナ・コイ・ウナギは食料として利用されていた(というより,食べるためのフナやコイを春から初夏のうちに池に放し,ほどよく育ったものをつかまえて利用していた).池によって住んでいる生物の種類は様々で,水を抜いたこのときは,生物相を把握するにも絶好の機会となる.



 ウナギカケ.水を抜いたため池でウナギを獲るための道具.
ウナギカケ.水を抜いたため池でウナギを獲るための道具.
淡路島の農家の納屋に眠っている.地元の鍛冶屋さんでつくっていたらしい.
2日目は,堆積した砂泥の流し出しをおこなう.上流側からポンプで放水して泥を溶かしつつ,池底の澪筋(みおすじ)(流路)に沿って並んだ作業者が,鋤簾(じょれん)で泥を押し流す.カッパを着ていても体中泥だらけになる.ときどき,池底から古い時代のジュースの空き缶など,時代を示す示準化石のようなものが現れて面白い.



ドロナガシが終わると,昔は「オチツキ」といって宴がおこなわれたらしいが,今は道具を片付けて解散となる.帰り際に,コイトリでつかまえておいたタイワンドジョウ,オオクチバス,フナ,コイなどをいただくことが多い.ときにはウナギをもらうこともある.これを持ち帰って,その日の夕方に学生寮の集会室で調理して食べる.当研究科のうちうちのオチツキだ.


ドロナガシに参加することで,ため池の構造,生物相,農村でのため池の管理体制などがちょっとわかるようになる.漁師の人たちや農家の人たちとの会話からは,地域のさまざまな魅力や課題に気づくこともある.特に何が,というわけでもないが,2年間の島暮らし・里山暮らしの期間中には,地元の人となるべく多く交流することで,島や里山の解像度が高まり,いつか自然環境の技術者・専門家として働くときの基礎がしっかりしたものになると思う.
地域の人たちといっしょにため池の水を抜いてみたい人は,ぜひ,淡路島に来て!