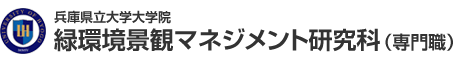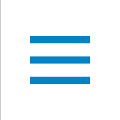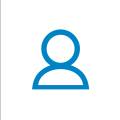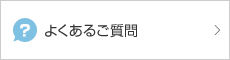2023年7月から11月にかけて東京都現代美術館で開催されていたデイヴィッド・ホックニー展を見てきました。それほど高い関心を寄せていた作家ではなかったのですが、独特の風景画をメインビジュアルとしたポスターに惹かれ、展示を見て回ることにしました。私は園芸療法士として長く仕事をしてきて、現在は園芸療法士の養成と園芸療法に関する研究をしています。なぜ植物との関わりが人の癒しにつながるのだろうか、そんなことを考える時、植物や風景をモチーフとした芸術作品を見たり読んだりすると、人が植物や自然、風景に惹かれる根源的な理由が見えてくるような気がして、そうした作品群に多く触れるようにしています。
今回の展覧会は現在86歳になるホックニーの画業を振り返るもので、若い頃の作品もとても格好良かったのですが、生まれ故郷であるヨークシャーや近年移住したノルマンディーの自然をモチーフにした作品群に興味を惹かれました。特に高さ1メートル、長さが90メートルにも及ぶ長大な作品「ノルマンディーの12か月」には圧倒されました。これはコロナ禍のロックダウン中に、iPadを用いて描かれた絵巻のような作品で、90メートルの作品の前を歩くと、彼の地の季節の移り変わりを早送りするように体感できる興味深い体験ができました。それとともに、コロナ禍において身近な自然に目を凝らし、その移り変わりを記録するという営みに、どこか共感も覚えたのでした。

コロナ禍においては、密閉空間や、人との密集や密接を避けざるを得ない状況から、緑地や公園に出かける人が増えたり、自宅で植物を育てる人が増えたりしたといわれています。感染症にかかったのではないか、知らないうちに誰かにうつしてしまったのではないか、それによって誰かの命を奪ってしまうのではないか等、それまでの暮らしでは感じることのなかった強い心理的ストレスを緩和するものとして、植物や自然は多くの人の役に立ったのではないかと思います。ホックニーもごく身近な自然にじっくりと向き合い、作品を描く中で救われた部分もあったのではと推測しています。先ほどホックニーに共感を覚えたと書きましたが、私はコロナ禍の時期、自身の生まれ故郷である北海道の十勝にいて、毎朝家の近くの公園を散歩しては写真を撮るということをしていました。

撮りためた写真をあとから眺めてみると、季節の移り変わりと、その時の情勢そして自分の心情も色濃く写しとっているように感じます。今はそのように緑の中を歩いたり写真を撮ったりしたいという気持ちは薄れていて、あの時、どうしてそのような行為に至ったのか、不思議に思うほどです(どうしてあれほど毎日早起きできたのかさっぱりわかりません)。勝手な想像ですが、ホックニーもきっと夢中で描いていたのではないかと思います。しかし、そうした行為にこそ、人が植物に惹かれ、植物に癒されることの理由が潜んでいるのでしょう。言語化や数値化が難しいものかもしれませんが、植物をモチーフとした芸術作品やその制作過程の多くに共通して見られる心性のようなものもあるのではないかと思っています。芸術鑑賞を重ねながら、いつか自分の中にその答えを持つことができるといいなぁと考えています。おそらくそれは、園芸療法を誰かに提供する上でとても大事な人間理解につながるものとなるでしょう。