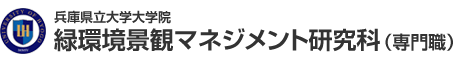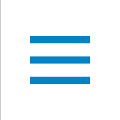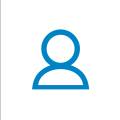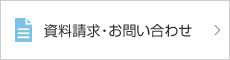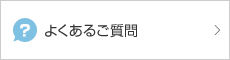「前栽」と書いて「せんざい」と読みます。
我が国最古の造園に関する書物と言われる「作庭記」も、江戸時代以前は「前栽秘抄」と呼ばれていたとされ、現在私たちが「庭(にわ)」として意識する空間は、本来「前栽」と呼ばれていたのではないか、と私は考えています。
実際、私の実家(姫路市郊外の農家)にも小さな庭がありましたが、農家生まれの無骨な祖父も父親もその空間に対してこじゃれた「にわ」などという言葉を使っていませんでした。というか使えなたった、という方が正しいのかも知れません。
「前栽の掃除をせなあかん」「前栽に水やらなあかん」などと播州弁で話していたことを思い出します。
そのような実家の前栽も建て替えとともになくなり、駐車場となってしまいました。これと同じように、私たちの周りからも「前栽」という言葉は消えてしまいました。

しかし、このような前栽は、今でも農村地域の農家に行くと立派なものがたくさん残っています。

また、このような空間の持ち主さんのなかでもこれらを「ニワ」と呼ばず、「センザイ」と呼ぶ方はたくさんいらっしゃると思います。
さて、このような前栽のあるお宅におじゃますると、そのお宅に漂う風格のような空気感を感じることが多々あります。
その風格を醸し出すのは、玄関に飾られた生け花であったり、客間に飾られた趣味の作品であったり、差し出されるお茶が立派な茶碗と抹茶と地元の和菓子であったり、そして主人の装いが和服であったり、と客人を迎えるしつらえのひとつひとつが「おもてなし」の心の表現となっていて、それが客人に伝わってくるのです。
さらに少し長居をして、お話などしていると、そこにあるものの話だけではなく、休日の過ごし方に及び、そこで踊りや謡いの稽古、陶芸、木彫、三味線、俳句、習字、盆栽・・・とどんどん話が広がります。
これらは、いわば古くからの日本人の「たしなみ」といえるでしょう。
昔の日本人は、庶民であっても文化人として備えておくべき素養を認識し、できる範囲でそれを身につける、という努力をしている人が多かったのだと思います。
しかし、高度経済成長期以降、それらのものは「古くさいもの」として見なされることが多くなりました。
洋風なものが「かっこいい」ものであり、以前の日本人が文化的で身につけるべきものと考えていたものが、古くさいものという認識になってしまったのです。
現に、高度経済成長とともに育ってきた私自身は、恥ずかしながらそのような「たしなみ」として、客人をお迎えするとき披露できるものが何ひとつありません。
しかし、地方部の農村地域のお宅では、今でもそのようなたしなみがごく普通に生活のなかに根付いていて、暮らしの一部として営々と受け継がれています。

そのような「日本らしい生活文化」が、今海外から注目されています。せっかく日本に行くのだから「日本らしいもの」を感じたいというのは当然のニーズでしょう。
そして、それらのたしなみの背景にある日本の精神性にも気づき、それらを「Cool!」と評価するのだと思います。
日本人は、都会が「かっこよく」て、田舎が「いなかくさい」と思いがちですが、外国人から見ると、都会はどこでも同じ、日本の田舎こそが「Cool!」という感覚なのでしょう。
コロナの影響でインバウンド観光は、今ほぼストップ状態ですが、これが終息するとその流れは必ず復活すると思います。
そして、その流れ、特にリピーターは都会には飽きて、田舎へ向かうことでしょう。
私は、その流れを前栽と生活文化のセットで受け止め、インバウンド観光の流れを地方部のあちこちに向けるプログラムづくりの試行を但馬地方で行ってきました。
Traditional Cultural Activities in Traditional Villages, Meet local people, experience local life
そのなかで、海外の方々のこれらのプログラムに対する「支払い意思額」などもわかってきました。
今、これらの試行はコロナの影響で中断していますが、早くこのプロジェクトの復活を願っています。
それにより、田舎が直接海外とつながる仕組みを確かなものにしていきたいと考えています。
そして、そのつながりの基盤は、庶民の家と暮らしのなかにある「前栽」と「たしなみ」だと改めて感じているのです。