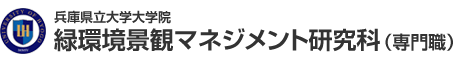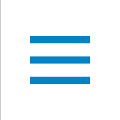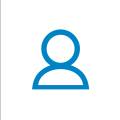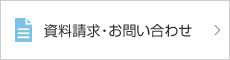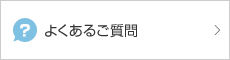公園緑地の計画論は、計画的かつ機能的にネットワークさせるモデルから、近隣住民の利用や活動を優先したActivity-based Modelへと大きく転換しています。このようなコミュニティ活動の場としては「公園」が日本では主に使われていますが、防災や子育て支援、健康づくりなど、現在発生している多様な分野横断型の地域課題解決には、共通して“次世代の担い手育成”という機能が関係していることから、「学校」を拠点にした地域づくりが有効との考えが米国では主流であるように思います。

具体的に、米国ニューヨーク州を中心に整備されている「Schoolyard Park」は、学校の校庭を公園のように再整備し、放課後や週末にコミュニティに開放しています。実際に中をみてみると、基本は子どもたちの運動の場なのでグラウンドベースなデザインですが、透水性の人工芝やウッドチップを使っていたり、アスファルトにペイントして温度上昇を抑えたりと、グリーンインフラな機能を持たせて地域に貢献されています。またレイズドベッドの菜園やポリネーターの庭など自然との接触機会の場もあり、地域のコミュニティガーデンに設置されているコンポストから土が供給されるなど、地域との繋がりも確認できます。利用面ではお祭りや映画鑑賞会など、大半が遊びやレクリエーションとして使われるようですが、特に地域から好まれるのはエクササイズや美術のプログラムなど、心身の健康に関するプログラムのようで、日本でも地域コミュニティと連携するきっかけとしてこのようなプログラムを用いることは有効ではないでしょうか。結果、約110万人の市民が徒歩10分以内でSchoolyard Parkを利用できる生活環境を得て、多様なコミュニティ活動が展開されています。




その他、カリフォルニア州でも「Living School Ground」と呼ばれる、校庭をエコロジカルな環境へ改善する活動が盛んで、特にコミュニティと協働することによって、お互いの親密度が高まり、子どもたちが身体的・精神的・社会的健康を得ることに繋がるとされます。
さらに米国だけでなく世界で展開されている「Edible Schoolyard Project」は、学校菜園とキッチンプログラムが融合した取り組みで、健康と栄養、適切な土地の管理、コミュニティへの貢献など、多様な価値を有しています。校庭には、ハーブや野菜の庭、バタフライガーデン、コンポストエリア、温室、ネイティブガーデンなど多様な緑空間が整備され、栽培活動だけでなく収穫物を加工したり、販売したり、それらを食するパーティが開催されたりするなど、多様なコミュニティと連携したプログラムが行われています。日本では農体験を通じて植物の生長や収穫を学ぶプログラムが多いですが、米国では自分が農家や料理人になったつもりで、何をしなくてはならないかということを学ぶプログラムであることから、どういう調理が必要か、どういう売り方が必要か、そういう思考を鍛えています。ファーマーズマーケットに行って売るなど、地域連携も欠かせません。



以上のような学校の校庭を舞台にしたコミュニティとの協働活動を通じて、子どもたちは多様な大人と接する機会を得ます。近隣住民や保護者の方々、お年寄り、大学生、あるいは、料理が上手な人、大工作業が上手な人、農作業ができる人、などなど様々です。結果、米国のEdible Schoolyard Projectを体験した子どもたちの中には、料理人を目指す子どもがいたり、農家になりたいという子どもが出てきたりするそうです。
考えてみれば日本の子どもたちが普段の生活の中で出会う大人は、学校の先生と、両親と、塾の先生ぐらいではないでしょうか。これまで都市公園で蓄積してきたコミュニティデザインの経験を、これからは学校の校庭で展開することで、地域コミュニティを豊かにするだけでなく、子どもたちの社会との接点を多様にすることが出来るのではないでしょうか。